フランスで子育てして3年、親の目から見て、日本とはこういうところが違うんだなあということを紹介していきます。
今後フランスで子育てする人の参考になればうれしいです。
私は子供が3人います。学校は、現地のキリスト教系の私立学校です。
教育言語はフランス語、幼稚部と小学部を経験しました。
日本では幼稚園まで経験しており、小学校は自分の時の体験をもとに比較しています。
そのため、日本の学校事情についてはふるい情報が混じることをご理解下さい。
では、フランス子育てのよかったこと・困ったことを紹介します。
フランス幼稚園小学校よかったこと
親が協力する行事が少ない
これ案外大切です。
幼稚園の時点で、季節ごとにイベントがあり、両親のどちらかが手伝いに駆り出されてました。
そして、幼稚園側も手伝いがある前提でイベントをやっています。
運動会や演劇、もちつきや夏祭りなど、イベントがたくさんあり楽しかった半面、やはり大変でした。
そういう意味では親の手伝いが必要なイベントが一切ないフランスは、共働き前提の社会構成になっているんだなと感じました。
昼休みが長い
子供たちは遊ぶのが大好きです。
そのため、2時間近い昼休みを楽しみに学校に行っています。
食事時間も含まれていますが、友達と一緒に遊べる時間が長いのはやはり嬉しいようで、今日はだれだれと遊んだ! という話をしてくれます。
学校に早く馴染めたのは昼休みに長い時間を学校の友達と過ごすからかなと感じました。
髪型服装が自由
校則らしい校則はありません
そのため、髪型や持ち物は自由です。
さすがにゲーム機やおもちゃは持ち込み禁止ですが、ベイブレードは持ってきている子供がいました。
また、ビー玉遊びも大人気。
服装も制服がなく、学校指定で何か買うということはありませんでした。
筆箱やペンなどの文房具を買うようには支持されましたが、ここの文房具屋で!とか、この中から選んで!ということはありませんでした。
小学1年生から6時間授業 幼稚園も同じ時間に終わる
幼稚園も小学生もお迎えは17時ちょっと前です。
そのため、良く日本で聞く小1の壁は存在していませんでした。
これは幼稚園も小学校も一緒だったので、子供が二人以上いる家庭には大助かりでした。
加えて、ギャルドリーという延長保育システムもあり、
朝7時40分から、夕方は18時過ぎまで預かってくれます。
このシステムも幼稚園と小学校で時間が一緒です。
年間契約もできるようになっており、これも共働き前提の仕組みだなと感じました。
いじめ問題への対応が早い
フランスではいじめた側に指導が入り、改善が見られなかった場合はいじめた側が転校するというシステムになっています。
我が家は子供がフランス語ペラペラではなかった時代に、何かあれば相手を指導するかちゃんと言ってね、と先生から気遣ってくれました。
小さいころにいじめられていた身としては、このシステムは日本でぜひ取り入れてほしいです。
フランス幼稚園小学校困ったこと
水曜日が休み
フランスの幼稚園、小学校は週休3日です。
なぜか水曜日がお休みです。
両親が働いていると、当然どこかに預けることになるため、そういった仕組みは充実しているようです。うちは専業主婦なので利用しませんでしたが、子供からすると水曜日は水曜日でどこかに行けて楽しそうでした。
でも預けると出費が…という面については、所得に応じて費用が変わる預かり保育が準備してあります。
ただ、海外赴任者は高給取りに分類されるためあきらめましょう。
6週間行くと2週間休み
フランスの学校は9月から始まります。
6週間たち、10月後半には秋休暇があります。
6週間たち、12月下旬はクリスマス休暇です。
1月に学校外再開して6週間、2月後半はスキー休暇です。
6週間たち、4月後半には復活祭でイースター休暇です。
そして6週間たつと、2か月の夏休み!
めちゃくちゃ少なく感じますよね。
でもこれがフランスの普通です。
子供が学校に行っていると親は平和だなあというのを休暇(バカンス)中に実感します。
そして、この時期をターゲットにしたアクティビティ付きの預かり保育が充実しています。
芸術だったりスポーツだったり様々です。
行政主導の安いものもあるので、ぜひ探してみて下さい。
Centre de loisir + 街名 で、出てくると思います。
子供の言うことを信じていいかわからない
これは子供同士のトラブル以外にも、先生が言ってた!と自信満々に言ったことが間違っていたことがあるためです。
あとは、なぜか子供が言ったことが正しいことになっており、お迎えに行ったら「え、今日は延長保育でしょ?」と先生に確認されたことがあります。
日本語でさえ言った言わないが生じることがあるので、言葉が変わると余計にこういう問題が起きます。
できるだけ信じるようにはしているのですが、念のため先生に確認しておくことが増えました。
先生のストライキ
ストライキは日本にはなじみがないですね。
政府の方針に反対して、仕事を休むことをストライキと言います。
ストライキしてデモ行進に参加して、自分たちの意見をアピールするのがフランスの普通です。
なお、学校の先生がストライキすると、臨時講師が面倒を見てくれます。
ストライキに参加する先生が多いと、学校から「子供たちをできるだけ家で過ごさせてね」と連絡が来ます。
ストライキは権利だから仕方ないね、と諦めるのがフランス文化です。
学校へや送り迎え必須
フランスの小学生には集団登校という概念はありません。
学校までは親が送っていく、迎えに行くのがフランスの普通です。
安全ではあるものの、自立という意味では大丈夫か? と心配にもなります。
日本の治安がいいというのは確かにあるんでしょうが、もうちょっと自立してほしいな、とも思います。
さいごに
日本とフランスでは学校の仕組みが違い、社会の仕組みが違います。
海外赴任中に子供が学校に通う場合、戸惑うことは多々あるでしょう。
そういうときは先輩がたや、日本人コミュニティ、その他相談先を探しておきましょう。
自分が苦労したことをどうやって解決したか、どうすればいいかきっと助けになってくれるはずです。
私の助けでよければコメントかツイッターからどうぞ聞いてください。
よき海外ライフを送れることを願っています。
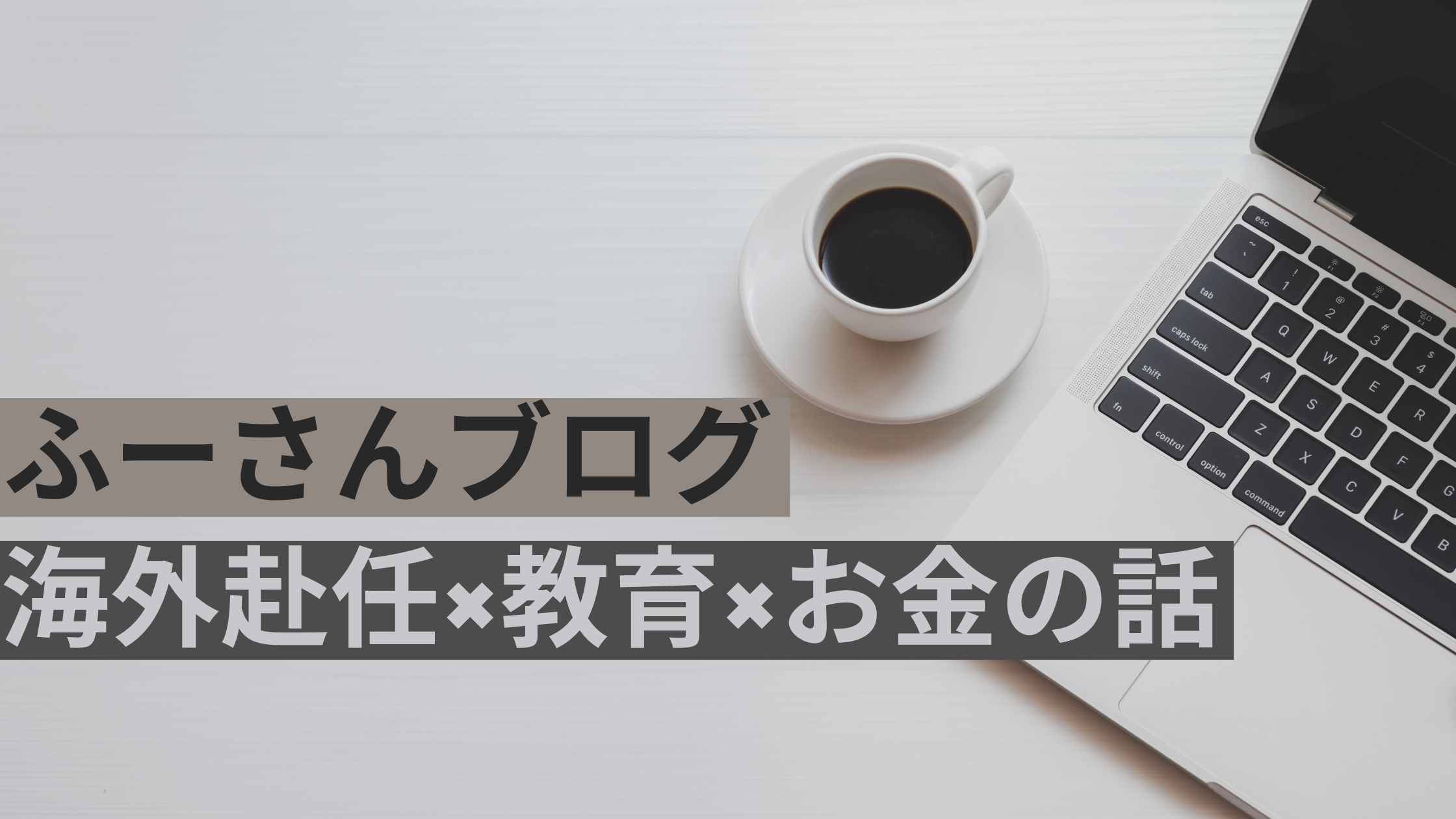



コメント